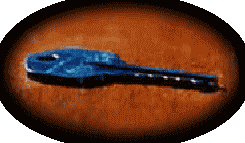
Review 不安の愉しみ
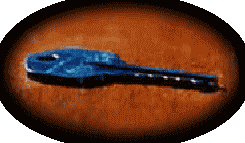
MULHOLLAND DRIVE (2001)
上映時間 146分 製作国 アメリカ 初公開年月 2002年2月 監督 デヴィッド・リンチ 出演 ナオミ・ワッツ
ローラ・エレナ・ハリング
ジャスティン・セロウ
アン・ミラー
ダン・ヘダヤ
マーク・ペレグリノ
マイケル・J・アンダーソン
ロバート・フォスター賞歴 アカデミー賞
監督賞(デヴィッド・リンチ)ノミネート
カンヌ国際映画祭
監督賞(デヴィッド・リンチ)受賞
NY批評家協会賞
作品賞 受賞
LA批評家協会賞
監督賞(デヴィッド・リンチ)受賞
STORY
真夜中のマルホランド・ドライブで起きた車の衝突事故。一人助かったブルネットの女(ローラ・エレナ・ハリング)は傷をおいながらもハリウッドの街までたどりつき、ある留守宅へ忍び込む。そこは女優ルース(マヤ・ボンド)の家だった。
翌日、ブロンドのベティ(ナオミ・ワッツ)は、女優を夢見て、叔母のルースを頼りにオンタリオからハリウッドヘやってきた。ルースはベティのためにオーディションを手配し、留守中のアパートを貸してくれたのだ。ベティが部屋を見て回ると、バス・ルームにブルネットの女が。リタ・ヘイワースのポスターから、とっさにリタと名乗った女を叔母の友人と思いこむベティだったが、すぐに見知らぬ他人であることを知る。リタは泣きじゃくりながら記憶を失ったと打ち明ける。手がかりを求めて開けたバッグには大金と不思議な青い鍵。同情と好奇心からリタの記憶を取り戻す手助けを申し出るベティ。
叔母が手配してくれたベティのオーディションは成功。同じスタジオでは新進監督のアダム・ケシャー(ジャスティン・セロウ)が主演女優のオーディションをしていた。ベティとアダムは何かを感じ、一瞬にして惹かれあう。
その後、リタがダイナーのウェイトレスの名札から思い出した「ダイアン・セルウィン」という人物が住む場所を訪ねる。二人は探し当てた部屋をノックするが返事はない。窓から侵入し寝室へ入ると、そこには腐乱した女の死体が。この死体は誰なのか?リタは何者なのか?その夜、二人は同情以上の感情を抱きあい、愛し合う…。
劇場で映画を観ている最中、トイレに行きたくなってしまった。隣の友人に告げてから大急ぎで用を足して暗い館内に戻ってくる。同じ座席に戻ったはずなのに、どことなく異質だ。隣に座っている友人は同じ顔をしているが、私の知っている友人とはどこか違っているような気がする…。
たとえばこんなふうな感じで、リンチの映画を見ていると不安になる。しかし怖かったり不快であったり…という感情ではない。
中国の故事に「胡蝶の夢」というのがある。荘周という男が蝶になった夢をみる。夢からさめたとき、自分が蝶になったのか、もともと蝶である自分が荘周になったのか、わからなくなってしまった…という話。リンチの映画からうける不安感は、この感覚に似ている。
「マルホランド・ドライブ」はあちこちで謎解きが試みられている。上に挙げたストーリーはこの映画のほんの一部だ。複数のエピソードが同時に進行しているのでストーリーをまとめるのはむずかしい。そのストーリーの謎をめぐって、日本の公式サイトや本などでも、あれこれと攻略されているようだ。先のアカデミー授賞式では、司会のウーピー・ゴールドバーグが「授賞式は長いけれども『マルホランド・ドライブ』についての解釈をする時間よりは短いから…」なんてギャグで会場をわかせていたし、フランスの公式サイトでは10のヒントが挙げられてもいた。
ブルー・ボックスを開くまでの前半を夢(もしくは現実)、後半を現実(もしくは夢)という解釈や、ベティとダイアン、リタとカミーラが、それぞれパラレルなワールドの住人だという解釈などなど、謎解きのおもしろさというのは確かにあると思う。しかし得体のしれないモノに意味を持たせると、とたんにつまらなくならないだろうか。もしかしたら「マルホランド・ドライブ」に意味を持たせようと試みる人たちの多くは「不安」なのかもしれない。意味を持たせることで安心したいのか。私は、その「不安」をあえて愉しんでみたいと思う。
リタの寝言によって二人が出向いた「クラブ・シレンシオ」。
ここは一番不安で一番好きなシーン。
お静かに
お静かに
すべてはまやかし
すべてはテープに録音されたバンドの演奏
奇妙なMC、奇妙なパフォーマンス。魔術師、青い髪の女。そして「泣き女」のまやかしの歌。
(「PLEASE RAISE VOLUME 3db HOTTER THAN NORMAL=通常より音量を3デシベル上げてください」という指示書がリンチから配給会社に送られてきたというが、クラブ・シレンシオのシーンにおいて、それは効果を発していた)
歌を聴きながら涙を流すリタ。そして震えがとまらなくなるベティ。夢か現実か。自分の存在が不安で痙攣はとまらない…。
リンチはこの作品を「ラブストーリー」と語っている。じっさいベティ=ダイアンに感情移入して見ると、不安と、そして切なさで胸がいっぱいになる。夢からさめたあとのさびしさにも似た切なさ…。
どの登場人物に感情移入してもかまわない。感情移入しなくても、「ブルーベルベット」のジェフリー(カイル・マクラクラン)のように、クローゼットから覗き見する感覚でもいい。とにかく上映が始まったら早めに身をゆだねてしまうことだ。リンチが罠をしかけたと仮定して、その罠に抗う鑑賞方法もあるだろうが、私は「マルホランド・ドライブ」の世界を「感じる」だけにした。
人工着色料のようなジルバシーン
マルホランド・ドライブの闇
ハリウッドのわざとらしい光
黄色い皿にパプリカの赤
黒いスーツに飛び散ったショッキング・ピンクのペンキ
白いナプキンに吐き出されたエスプレッソ
クラブ・シレンシオの青い髪の客
フィフティーズなベビーピンクのルージュ
小径をゆく黒いドレスの美女
青い鍵とブルー・ボックス
リンチの映像はどこをどう切り取っても一枚の絵(瞬間の美しさ)になると今さらながらに感心する。画家、写真家、また家具デザイナーとしての才能も評価されているが、シーンからシーンへのつながり、物語の流れよりも、アイデアの積み重ね、いやコラージュといったほうがいいかもしれないが…そういう作業に重きをおき、また言葉や感情、意識下にあるモノを視覚化することに長けているので、イメージだけで魅せることができるのだろう。
これはシュルレアリスムの手法にどこか似ているように思う。「イレイザーヘッド」の押し寄せてくる家具のイメージが、「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル、サルバドール・ダリ)におけるピアノと腐った驢馬の屍体をひっぱる男のイメージに重なり、「ブルーベルベット」の切り落とされた耳にたかる蟻が、「アンダルシアの犬」の掌にたかる蟻に重なる…と勝手にこじつけてしまったからかもしれないが。
リンチの絵はどちらかというと抽象画といった雰囲気だが、映画からは夢をコラージュしたようなシュールな映像詩といった印象を受ける。
またこの作品にはリンチの遊び心も随所にみられる。まず二人の女性のネーミング。
「リタ」はエピソードの通りリタ・ヘイワース、「ベティ」はベティ・デイビスだろう。「ダイアン」は、「ツインピークス」でクーパー捜査官(カイル・マクラクラン)がテープレコーダーに呼びかけていた名前。「カミーラ」はロジェ・バディムが監督した「血とバラ」(レ・ファニュ原作)に登場する女吸血鬼カーミラを連想させる。連想したのは名前だけではない。「血とバラ」は吸血鬼映画であると同時に、レズビアン・シーンでも有名なのだ。
それから謎の男Mr.ローク(「ツインピークス」の踊る小人役でおなじみのマイケル・J・アンダーソン)が座っている部屋は、ひだのたっぷりとしたカーテンがあり「ツインピークス」の赤い部屋を思い起こさせる。
クラブ・シレンシオでの奇妙なMC「すべてはテープに録音された…」というくだりでは、リンチ自ら心因性記憶喪失(サイコジェニック・フーガ)と語った「ロスト・ハイウェイ」の始まりとなるビデオテープと重なる。「ロスト・ハイウェイ」のフレディ(ビル・プルマン)は「記憶は常に自分なりに」という。テープに記憶された現実と脳内に記憶された現実は違うのか。現実と夢…正常と異常はどう違うのか。「ロスト・ハイウェイ」は「マルホランド・ドライブ」のプロローグでもあったのだろうか。
また老人の使い方が巧いのもリンチならでは。(「ストレイト・ストーリー」はもちろんだが、私は「イレイザーヘッド」の動かないおばあさんを支持する)ベティを応援する裏で、嘲り高笑いする老夫婦の不気味さは秀逸!
唐突に登場するわけのわからないキャラクターは、リンチ作品では珍しくも何ともないのだが、必然性のない風貌のキャラクターというのは理由なしに嬉しいものだ。
…と、こんなふうに、自らをパロディ化するリンチのユーモアも存分に愉しめる。
「不安」について話を戻そう。
旧知の人物が全然違う役で登場する夢を見たことはあるだろうか。家族なのに他人の役であったり、会ったことのない憧れのスターが自分の恋人であったり、仲の良い友人が敵役であったり…。夢からさめたあとに、恥ずかしくなったり涙を流してしまったりする、あの余韻。心地よい不安感。
「マルホランド・ドライブ」の場合
・ベティはダイアン、リタはカミーラと、名前も境遇も違う。A世界でベティとリタは愛し合っている。B世界のダイアンは憎しみと嫉妬からカミーラに殺意を抱く。
・映画監督のアダム・ケシャーは同じ名前と職と顔(マユゲの濃さが違う?)だが、B世界では浮気な妻の存在はなく、カミーラと恋人同士だ。
・アパートの管理人ココは、B世界でアダムの母親である。
・ダイナーのウェイトレスはダイアンからベティという名札に変わっている。
・夢で恐ろしい男の幻影を見たという濃いマユゲの青年ダンは、B世界では自分が見た夢の中の登場人物になっている。
・ドジな殺し屋はB世界でも殺し屋だが、カミーラの殺人を請け負い成功したような感じだ。
・A世界でアダムをかくまっていたホテルのマネージャーとクラブ・シレンシオのMC役は同じ男。(クラブ・シレンシオからB世界に突入していたのだろうか?)
・アダムに不思議な暗示を残すカウボーイ
・ブルー・ボックスを手にした恐ろしい風貌の浮浪者
・高笑いする老夫婦
…彼らは同じキャラクターで二つの世界を行き来しているようである。
・そしてB世界のマルホランド・ドライブとハリウッドの間にあるアダムの邸宅ではパーティーが催され、すべての登場人物が一同に集っている。ハリウッドのすべてを司るかのようなMr.ロークもA世界に登場した他の人物も…。
二つの世界の関係に意味を持たせることは可能だろうが、意味を持たせなくても十分に愉しめると思う。「マルホランド・ドライブ」は、得体のしれないモノ、理由のわからない不安、見飽きない悪夢…そういったモノに酔うために観る映画なのかもしれない。謎解きをする人も、身をゆだねて感じるだけの人も、またそのいずれでもない人も、リンチ・ワールドに引き込まれ、その余韻からなかなか抜けられないのは同じなのだ。
「イレイザーヘッド」は、21才で父親になってしまったリンチの不安のあらわれであったかもしれない。「ブルーベルベット」でジェフリー(カイル・マクラクラン)がクローゼットから覗いたダークサイドは、誰もが抱いている部分だから不安なのだろう。「ワイルド・アット・ハート」にしばしば登場する炎のイメージは、愛だけに生きようとするセイラー(ニコラス・ケイジ)とルーラ(ローラ・ダーン)の不安の裏返し。同じくロード・ムービ―「ストレイト・ストーリー」で、リンチ・ワールドに馴れたファンは不安になった。「ロスト・ハイウェイ」の暗い闇。環のほころびがみつからない。ヘッドライトの先の闇はいつまで続くのか…。そして「マルホランド・ドライブ」はいつまでも終わらない。
(2002年3月脱稿)